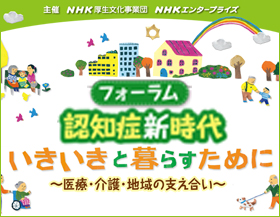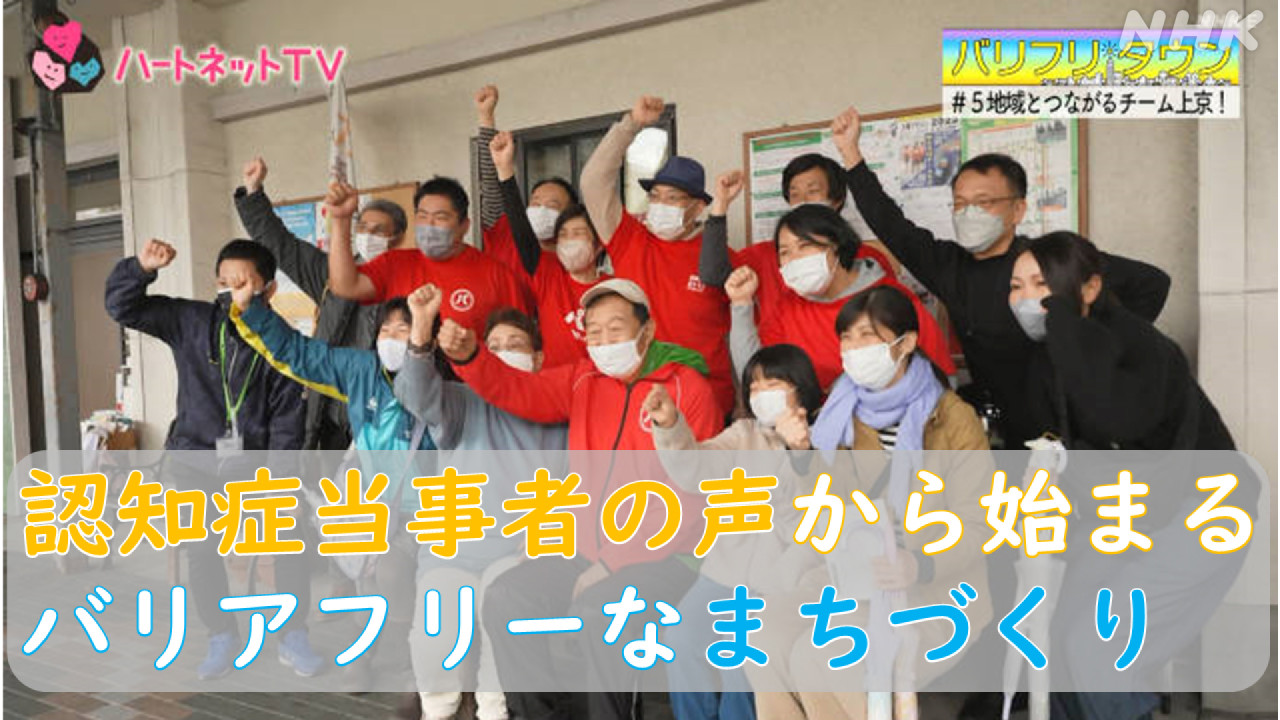第9回「認知症とともに生きるまち大賞」受賞団体決定!
公開日:2025年11月14日
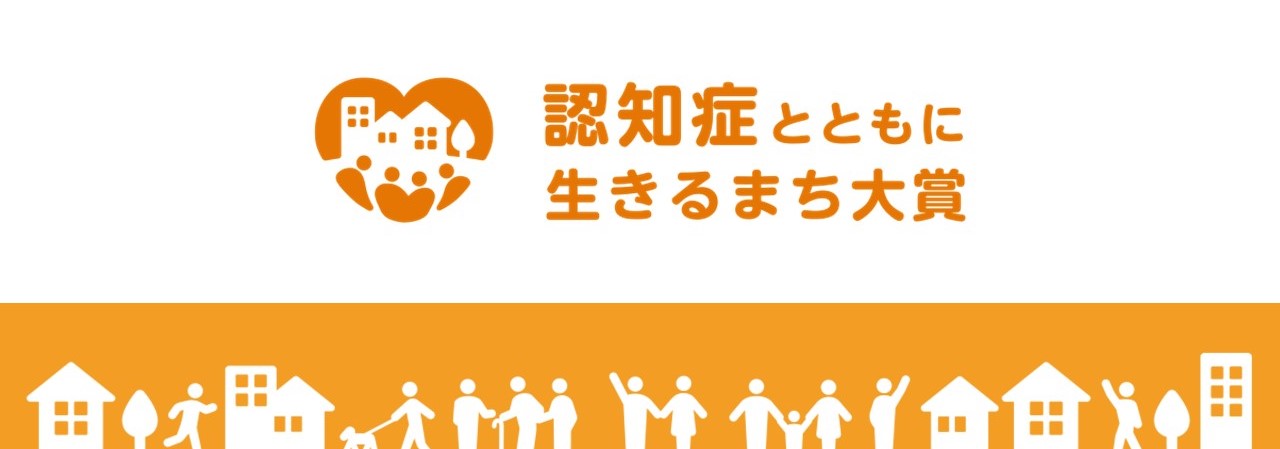
認知症になっても安心して暮らせるまちづくりの取り組みを募集して、表彰する「認知症とともに生きるまち大賞」。このほど選考委員会が開かれ、今年の表彰団体(本賞4件、特別賞2件)が決まりました。
受賞団体
【本賞】
- 認知症の人が行きたいところへ行こうプロジェクト(東京・町田市)
- マイWayサードプレイス(神奈川・川崎市)
- ちばるグループ(愛知・岡崎市)
- ばあちゃん喫茶(福岡・福岡市/うきは市ほか)
【ニューウェーブ賞(特別賞)】
本賞とは別に、全国の若い世代に広がることを期待して、2つの高校の活動を、ニューウェーブ賞として表彰します。
- 桂桜オレンジプロジェクト(秋田・大館市)
- 戸手高校カフェ(広島・福山市)
(掲載は地理的に北から順)
本賞
本人とともに地域の人たちとクラブチームがサッカー観戦を実現
認知症の人が行きたいところへ行こうプロジェクト(東京・町田市)
認知症の人が行きたい場所へ安心して行けることをともにかなえる取り組み。「もう一度、サッカーや野球の試合を見に行きたい」という本人の願いをきっかけに始まった。本人の懸念や楽しみなどの声を丁寧に聴きながら、地域の人々・医療福祉関係者・J1クラブチーム・市が一体となって体制づくりを行ってきた。市とクラブチームが連携協定を結び、サポーターを対象に「認知症サポーター養成講座」を開催。修了者がチケットの確保や当日のスタジアムへの送迎、「さりげない声かけ」や「座席への案内・試合説明」を担うなど、試合観戦を通じて「認知症の理解と自然な支えあい」と「もっと行ける」という思いが広がり、「認知症とともに生きるスタジアム化」が進みつつある。
【選考委員講評】
サッカー観戦に行きたいという一人の本人の願いを聞き流さずに、「その願いをいっしょにかなえよう!」と地域の有志が結集。活動はすべて本人たちの具体的な声をもとに設計・実施しているプロセスがすばらしい。取り組みの過程で、医療福祉関係者も含めた地域の人々・J1クラブチーム、市などがつながりあい、願いをかなえるためにそれぞれができる実践を積み重ねている。本人そして活動をともにしているそれぞれが、体験を通じて「どこへ行きたいか・どう生きるか」いっしょに考える機会になっており、「誰もが自分らしくともに暮らせる」まちづくりの原動力になっている。スポーツ観戦を始め、本人の「~へ行きたい」という素朴な願いをあきらめずに、地域の多様な人たちがつながりあうことで実現させていける可能性に満ちており、全国各地に広がっていってほしい。
トップに戻る
【選考委員講評】
サッカー観戦に行きたいという一人の本人の願いを聞き流さずに、「その願いをいっしょにかなえよう!」と地域の有志が結集。活動はすべて本人たちの具体的な声をもとに設計・実施しているプロセスがすばらしい。取り組みの過程で、医療福祉関係者も含めた地域の人々・J1クラブチーム、市などがつながりあい、願いをかなえるためにそれぞれができる実践を積み重ねている。本人そして活動をともにしているそれぞれが、体験を通じて「どこへ行きたいか・どう生きるか」いっしょに考える機会になっており、「誰もが自分らしくともに暮らせる」まちづくりの原動力になっている。スポーツ観戦を始め、本人の「~へ行きたい」という素朴な願いをあきらめずに、地域の多様な人たちがつながりあうことで実現させていける可能性に満ちており、全国各地に広がっていってほしい。
トップに戻る
自家焙煎珈琲を本人がともに企画・販売、出張カフェも
マイWayサードプレイス(神奈川・川崎市)
2013年、「若年性認知症の人の働く場」を当事者とともに開始。コロナ禍で仕事量が減ったことをきっかけに、新しい取り組みをと、「自家焙煎珈琲」づくりに挑戦。生豆の選別から焙煎、パッケージ、販売まですべて手作業で行っている。また近年は焙煎に加えて、様々な場所で「出張カフェ」を開催し、自分たちが焙煎した珈琲をふるまいながら地域の人と交流を深めている。本人たちの「働く」「集う」「つながる」を実現するための、自宅でも会社でもない“第三の居場所”として活動を続けている。
【選考委員講評】
一杯の珈琲に、本人たちの思いと力、可能性が詰まっている。焙煎などの作業はもちろん、商品企画などもつねに本人らが意見を出し合って決めて動いている。本人が「何かをしてもらう・言われてやる」のではなく、「どうすれば喜んでもらえるか」、客や地域のことを真剣に考えながら、時間をかけてゆっくり、息長く、時代や地域に応じた活動を創り出し続けている。薫り高くおいしい珈琲を通じて、自信や自分を取り戻し、仲間や地域の人たちと深いつながりを育みながら、お金も稼ぎだしている。認知症の本人とともに、どう時をともにし、何を語り合い、何を創りだしていくのか、全国各地の活動や私たち一人ひとりのあり方を問いかけている活動である。
トップに戻る
【選考委員講評】
一杯の珈琲に、本人たちの思いと力、可能性が詰まっている。焙煎などの作業はもちろん、商品企画などもつねに本人らが意見を出し合って決めて動いている。本人が「何かをしてもらう・言われてやる」のではなく、「どうすれば喜んでもらえるか」、客や地域のことを真剣に考えながら、時間をかけてゆっくり、息長く、時代や地域に応じた活動を創り出し続けている。薫り高くおいしい珈琲を通じて、自信や自分を取り戻し、仲間や地域の人たちと深いつながりを育みながら、お金も稼ぎだしている。認知症の本人とともに、どう時をともにし、何を語り合い、何を創りだしていくのか、全国各地の活動や私たち一人ひとりのあり方を問いかけている活動である。
トップに戻る
当事者が日常として働ける、地域の食堂
ちばるグループ(愛知・岡崎市)
雇用条件は「認知症であること」。当事者を一般雇用し、最低賃金以上の時給を支払う地域の食堂として、介護福祉士が2019年に「ちばる食堂」をオープンした。現在は3名の当事者を雇用し、週6日間営業している。2021年にはデイサービスと隣接してテイクアウト専門店「パーラーちばる」をオープン。また毎月1回開催する「ごちゃまぜ食堂ちばる」では、デイサービスの利用時間が終わった後、赤ちゃんから地域のお年寄りが誰でも無料で夕食が食べられる。地域のさまざまな年代の人たちが集い、交流する場となっている。
【選考委員講評】
単発のイベントで終わらせるのではなく、本人にとって、日常として働く場となっているところがいい。そんな場があるからこそ、本人たち一人ひとりが、それぞれの個性や、実は豊かに秘めている力を自然と発揮しながら活き活き活躍している姿は、次に続く本人や、家族、地域の人々、専門職や行政など、すべての人に感動や勇気をもたらすことだろう。「食堂」をやっていること以上に、本人たちの変化や地域の実情にしっかりと向き合いながら、この日常を持続・発展させていくための試行錯誤を、本人たちとともに粘り強く続けていることに価値がある。
トップに戻る
【選考委員講評】
単発のイベントで終わらせるのではなく、本人にとって、日常として働く場となっているところがいい。そんな場があるからこそ、本人たち一人ひとりが、それぞれの個性や、実は豊かに秘めている力を自然と発揮しながら活き活き活躍している姿は、次に続く本人や、家族、地域の人々、専門職や行政など、すべての人に感動や勇気をもたらすことだろう。「食堂」をやっていること以上に、本人たちの変化や地域の実情にしっかりと向き合いながら、この日常を持続・発展させていくための試行錯誤を、本人たちとともに粘り強く続けていることに価値がある。
トップに戻る
高齢者の力を地域の力に
当事者が店長 “ばあちゃん喫茶”(福岡・福岡市/うきは市ほか)
ある認知症の女性・Aさんは毎日、自宅でとんかつを揚げていた。それを地域に活かせないかと、NPO法人なごみの家が、こども食堂「なごみ食堂」で、とんかつをふるまう場を企画。一方、うきはの宝(株)は、75歳以上の高齢者が働ける会社として、さまざまな「ばあちゃんビジネス」を展開していた。福岡市の紹介で出会ったふたつの団体が連携して運営する「ばあちゃん喫茶」で、Aさんの揚げるとんかつ定食は人気のメニューに! 高齢であっても、認知症であっても、本人の力を地域の力として活かしていく取り組みである。
【選考委員講評】
企業とNPOが連携して収益を得ることで継続性を確保できている。ビジネスの視点やノウハウもフルに活かしつつ、本人の視点・思い・力に基軸にして、本人たちが自ら積極的に参加し、持っている力を十分に発揮しながら活き活き活躍する姿や場面を通じて、地域の様々な人に自然体の理解と交流が発展している点を高く評価する。全国のほかの地域の人たちにも、住み慣れた地域でともに暮らし続けていくためのいいヒントになるのではないか。
トップに戻る
【選考委員講評】
企業とNPOが連携して収益を得ることで継続性を確保できている。ビジネスの視点やノウハウもフルに活かしつつ、本人の視点・思い・力に基軸にして、本人たちが自ら積極的に参加し、持っている力を十分に発揮しながら活き活き活躍する姿や場面を通じて、地域の様々な人に自然体の理解と交流が発展している点を高く評価する。全国のほかの地域の人たちにも、住み慣れた地域でともに暮らし続けていくためのいいヒントになるのではないか。
トップに戻る
ニューウェーブ賞(特別賞)
高校生の“もっと”があふれ出す
桂桜オレンジプロジェクト(秋田・大館市)
はじまりは7人の高校生と教員のチャレンジ。そこに地域の専門職が加わりチームが始動した。高校の一室で2か月に1回開催する桂桜オレンジカフェ。市のカフェとも連携することで、相乗効果を生んでいる。高校生が各テーブルにつき、参加者の声に耳を傾ける。参加者たちも高校生が相手なのでリラックスして楽しんでいる。生徒たちからは「もっとオープンで親しまれる場所にしたい」「もっと地域とつながりたい」など、開催するたびに高校生の“もっと”があふれ出す。
【選考委員講評】
まず、学校・高校生が応募したことを歓迎したい。若い人たちからの発信が続くことで、まわりの人が認知症について“自分事”に感じるきっかけになる。全国の高校生同士で関わりを作ってこの取り組みが広がっていくことを期待する。
トップに戻る
【選考委員講評】
まず、学校・高校生が応募したことを歓迎したい。若い人たちからの発信が続くことで、まわりの人が認知症について“自分事”に感じるきっかけになる。全国の高校生同士で関わりを作ってこの取り組みが広がっていくことを期待する。
トップに戻る
県内初の高校生が運営する認知症カフェ
戸手高校カフェ(広島・福山市)
毎月1回学校の図書室で開催する認知症カフェ。広島県初の高校生が運営する認知症カフェとして、地域の方々と世代を超えた交流を深める場となっている。2024年、高校生たちが認知症について調べることから始まった。認知症サポーター養成講座を受講したり、他の認知症カフェを見学したり、何度も会議を重ねて、10月に第1回戸手高校カフェをオープン。以降、ミシンを使ったワークショップや参加者と高校生がチームになりゲームを行うなど趣向を凝らして実施している。
【選考委員講評】
始まったばかりだが、これから後輩へと代々つなげていってほしい。高校生ならではのオリジナリティーや努力の跡が見え、この取り組みは、学校のアイデンティティーになるのではないかという期待感が大きい。
トップに戻る
これまでの受賞団体
これまでの受賞団体は、「認知症とともに生きるまち大賞」特設ページでご確認いただけます。
応募期間
2025年4月1日~8月31日
応募数
45件
選考委員
永田 久美子(認知症介護研究・研修東京センター副センター長兼研究部長)
丹野 智文(おれんじドア代表、認知症当事者)
町永 俊雄(福祉ジャーナリスト)
和田 誠(認知症の人と家族の会 代表理事)
小野 洋子(NHKコンテンツ制作局 第1制作センター 福祉部長)