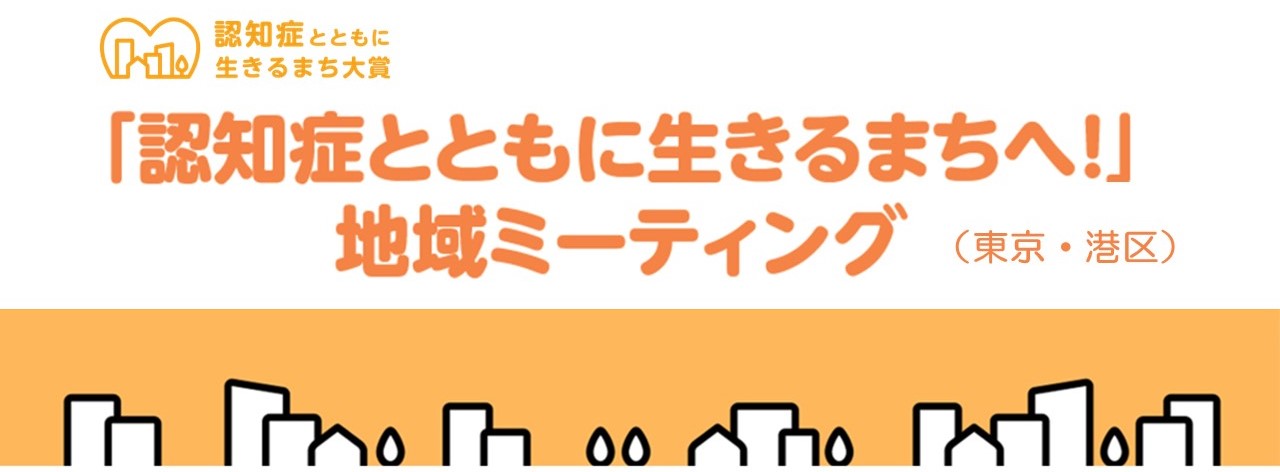「交流教室 デフリンピアンがやってきた!」を神奈川県平塚市で開催しました
公開日:2025年9月25日

今年11月に日本で初めて開催される、デフリンピック。
デフ(Deaf)とは、英語で「耳が聞こえない」という意味で、デフリンピックは聴覚に障害がある人のためのオリンピックです。
大会を前に、デフリンピックの選手によるデフサッカー教室を開催しました。
会場は、神奈川県立平塚ろう学校。聴覚障害のある子どもたちが学ぶ特別支援学校です。
講師にお呼びしたのは、東京2025デフリンピック日本代表の阿部 菜摘選手、岡田 拓也選手、岡田 侑也選手、國島 佳純選手です。

体育館には、中学部と高等部の生徒たち約30人と、先生たちが集まってくれました。
まずは講演の時間。選手たちが手話と声の両方で、デフリンピックのこと、デフサッカーのことをみんなに語ってくれました。
デフサッカーは、基本的には通常のサッカーと同じルールです。異なる点は、主審が笛に加えてフラッグを使用すること。試合中、選手たちは補聴器を外すことが義務付けられており、笛の音が聞こえない、聞こえづらいためです。選手同士は、アイコンタクトや手話でコミュニケーションを取るのです。
世界の舞台で戦った時の貴重なお話も聞かせてくれました。
「デフリンピックでは選手村っていうのがあって、試合が終わったあと、帰ってくる所が皆同じなんだよね。だから、戦って負けたときも、帰ってきたら戦った相手が目の前にいるの。すごくイヤ(笑) でもね、国際交流もいっぱいあるんだよね」
「ふだん日本で使ってる日本手話は、海外の選手には伝わらないの。選手村で、国際手話がわからなくて。でもね、身振り手振りで、海外の選手たちともわかりあえたよ」
「恥ずかしがらないで、自分を表現することがすごく大事だなって、勉強になりました」
 |
 |
 |
そこで、侑也選手がみんなに問いかけます。
「みんなの中には、陸上やってる人が多いんだね。デフリンピックの種目ってたくさんあるんだけど、平塚ろう学校の卒業生にはデフバレーボールの日本代表がいるんだってね!みんな、日本代表目指してます!っていう人、いる?手を挙げてっ」
生徒のみんなは気恥ずかしそうに周りを見渡していて、誰も手をあげません…。
でも侑也選手は、そんなみんなに強く声をかけました。
「そういうところは恥ずかしがらないで、胸を張って、自信を持って言ってほしい!口に出さないと伝わらないし、夢って叶わないから。みんな、自信もって!日本代表、目指してますって人、手を挙げてっ」
侑也選手の熱い気持ちに促され、手を挙げてくれる生徒が、どんどん増えていきます。
「おー!もっともっと!手を挙げよう! みんなそれぞれ今努力してることがあると思うんだけど、今後長い人生の道のりで、こういう大会がある、とか、具体的な目標を視野に入れて、モチベーションとして目指してほしいなって思います!」
叶えたい夢があったら、実際に周りにどんどんアピールしていい、そして具体的な目標を作る、そこから始まるんだよ、と力強く教えてくれました。
 |
 |
 |
そして生徒たちは実技に挑戦!
まずはボールに慣れるための「ボールフィーリング」のやり方を教えてくれました。1人1つずつボールを持って体験します。
- ボールを上に投げて、ボールが宙にある間に拍手をしてから受ける。
- ボールを上に投げて、その場で体を1回転させてから受ける。
- 2人で向かいあって、それぞれの足元のボールを相手に向かって同時に蹴ってパス。その時、ボール同士がぶつからないような軌道で蹴る。
- ペアで、相手の背中に向かってボールを投げて、投げられた方は背中にあたったらすぐ振り返ってボールが落下する前にキャッチ。
などなど、生徒と選手はボールを通して体を動かして交流し、距離も近づいていきました。
 |
 |
 |
次に、中学部と高等部に分かれ、選手と輪になっての座談会を行いました。
学校生活や進路など、様々な悩みごとが出てくるであろう世代の生徒たち。人生の先輩、さらに女子選手のお二人はみんなと同じく ろう学校の出身の先輩として、みんなで腹をわって話せる時間を作りたいと考え、この時間を設定しました。
講演で選手のことを知り、実技体験で選手と距離を近づけた生徒たちは、とても前のめりに選手たちの話を聞き入り、積極的に質問もしていきました。
【中学部座談会】
生徒「双子でサッカーをしていて、けんかすることはありますか?」
拓也選手と侑也選手は双子で、二人ともがデフリンピアンという稀有な選手です。
拓也選手「この前の代表合宿のときもけんかしました。やっぱりサッカーの中でお互いのやりたいこと、エゴがぶつかるっていうのはよくある話。これは双子だけじゃなくてチーム内でだってよくある話だね。プライベートでは、最近やっと仲良くなった(笑)」
阿部選手「最近?(笑)」
生徒「デフサッカーとデフフットサルの両立でたいへんなことは?」
阿部選手と國島選手はデフサッカー、デフフットサル両方の女子日本代表で、ワールドカップで世界一を経験したこともある選手です。
阿部「サッカーは外だけど、フットサルは体育館で、11人じゃなく5人で試合するしコートもゴールも小さいしボールの扱い方もちがう。サッカーはボールを足のインサイドで止めるんだけど、フットサルは足裏でとめて、運ぶ。そこの違いが難しいな。だからサッカーの合宿に行って、帰ってきてすぐフットサルのチームの練習に行くと、めちゃくちゃ足が痛い。今も痛い(笑)。女子デフサッカーはチーム数が少なくて、そんなふうに掛け持ちしてる選手がけっこう多かったんだけど、今は人口が増えてきて、サッカーとフットサルで分かれて活動が出来てきてる」
 |
 |
 |
【高等部座談会】
生徒「陸上の選手になるには何が必要ですか?」
侑也選手「陸上の選手にも知り合いがいるんだけど、みんな、食事にはこだわって気にしてたね」
國島選手「食事プラス、あと、睡眠も。トレーニングだけじゃなく最低限の休息は気を遣ってるね」
生徒「何歳までサッカーをやりたいですか?」
侑也「一生続けたい!日本代表として、なら、自分が必要とされる限りやりたい!」
國島「一生とは思ってないけど(笑)私も、日本代表としては、自分が必要とされる限りやりたい」
生徒「仕事はどんなことをしていますか?」
侑也「僕はIT関係の社内対応。業務時間は9時半から15時までで、そのあとは選手としてのトレーニングの時間をもらうっていう配慮をしてもらってます。皆、これから卒業したあとに、就職する人、大学に行く人、進路の悩みがある人も多いと思う。目標はなかったけど、國島さんみたいに、とりあえず就職選ぼうって就職選ぶ方法だってあるんだ」
生徒「國島選手は体育大学に進むことは考えなかったんですか?」
國島「うん、考えた。でも高等部にいるときには何になりたいかは思いついてなくて。目標が無いまま大学を選んで親に負担をかけるのはためらいがあったの。だから自分でお金を稼いで、やりたいことを見つけていこうっていう考えで、就職を選んだの。侑也選手は高校入った時から大学行こうと思ってた?」
侑也「僕は大学に入るまでは自分の聴覚障害に対して自覚がなかったの。高校のときから本気でプロのサッカー選手になるために大学に進むっていう気持ちがあった。で、そのまま大学に進んで、結果的にはデフサッカーにめぐりあって、デフサッカーで日本代表にたどり着けたのは、自分の中でいい結果だったのかなと思います」
選手たちの赤裸々なお話に、生徒たちは食い入るように耳を傾けて、質問も飛び交い続けました。
 |
 |
 |
最後は、デフサッカーの試合で選手たちにチャレンジしました。
中学部と高等部のチームにわかれて、選手4人対生徒チームの対戦です!
コートの周りで見守る生徒たちは、「目で見てわかる応援」、聞こえない人に伝わる応援として、手話を元にして作られた「サインエール」で応援していました。
全力で挑んでくる生徒たちに対し、選手たちも手加減なしで素晴らしい試合を見せてくれました。
この教室で、世界を舞台に戦う同じ障害を持つ先輩たちと交流したことを、生徒のみなさんがさらに自分の将来に可能性を感じて未来を切り拓く糧にしてほしい、と願っています。
 |
 |
 |
 |
 |
 |