オープンダイアローグフォーラム「寄せられたすべての声と ゲストの応答コメントをご紹介します」
公開日:2025年7月13日

2025年6月28日に開催したNHKハートフォーラム「オープンダイアローグを土台に 日本のこころのケアの近未来を考える」には、1600人を超えるお申し込みと、およそ1100通のメッセージをお寄せいただきました。出演ゲスト4名(森川すいめいさん・小澤いぶきさん・矢原隆行さん・高口恵美さん)と制作担当者で、お一人おひとりの声を大切に読ませていただきました。すべてのメッセージをフォーラム中にご紹介しきれなかったため、こちらのホームページで「すべてのメッセージ紹介」と「ゲストの応答コメント」を掲載させていただきます。さまざまな方の声を受け止め、わかちあう場になれば幸いです。
>>フォーラムの概要はこちら
※個別の質問等にお答えすることができない点、ご了承ください。
※配信時、音声の一部が乱れました。お聞き苦しい点があり失礼しました。
お寄せいただいたすべてのメッセージ
こちらからお読みいただけます(別ウィンドウが開きます)
1095件のメッセージをお寄せいただきました。上記リンクからぜひお読みください。
森川すいめいさんの応答コメント
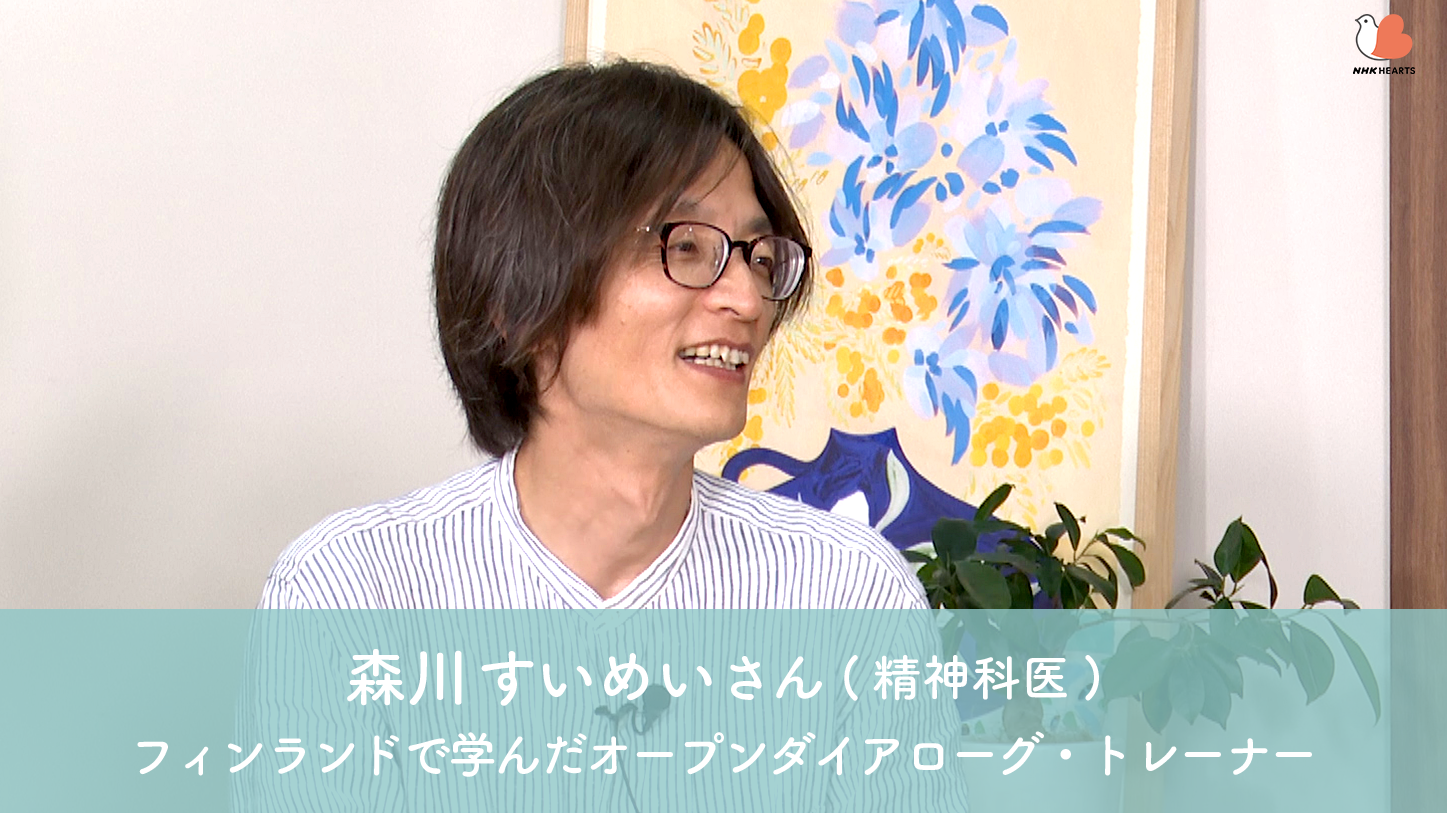
すごくたくさんの声にこころが動かされ続けています。
あらためて、13時から17時という長い午後のひとときを共に過ごしてくださった皆さまへ、こころからの感謝を伝えたいです。そして、この場を静かに支えてくださったスタッフの方々、一緒に登壇し言葉を紡いでくれた友人たち、場の安全を守り続けてくれた中野淳さん、そして3年という歳月をかけてダイアローグ(対話)を重ね、実現へ導いてくださったディレクターの林原摂子さん。本当に、ありがとうございました。
このフォーラムをつくるうえで、知識を一方的に伝える場にはしたくないと強く思っていました。支援する・されるという関係を超えて、経験を分かち合うこと。そのために、参加してくださる方々の声から始まる会にしたいと願いました。台本はなく、登壇者もその場その場で「今、ここ」に身を置くことにこだわりました。そうすることで、きっと新しいダイアローグが生まれ、これまで見えなかった景色が立ち現れると信じていたからです。
事前に寄せられた声のなかには、痛みがたくさんありました。孤立、支配、暴力。医療の現場だけでなく、学校や福祉、行政、企業など、さまざまな場所から届いた声には、胸が締めつけられるような切実さがありました。声を上げられない現実。権威や強い力によって閉ざされた世界。自分たちのいないところで物事が決まり、「従え」と言われること。ほかの選択肢が見えないこと。そうした現状を、ひとつひとつの言葉から感じとりました。
同時に、オープンダイアローグという、誰にでも開かれた、水平で対等なダイアローグの場に希望を託す声もありました。フォーラムのなかで紹介された声や、その場で寄せられた言葉には、「互いを尊重し合いたい」という願い、「尊厳を取り戻したい」という切実な思い、家族が背負う苦しみ、今まさに困難の渦中にいること――そうした痛みが、ぼくの身体の奥に残りました。
また、いただいた声とぼくたちとの会話とを聴きながら希望を感じてくださった方、実際に開かれた活動を始めて「やってよかった」と伝えてくれた方の声もありました。その言葉に、また新しい希望を見つけました。
オープンダイアローグは、ひとりひとりの声を大切にする。それは、尊厳そのものです。すべての声が聴かれることで、はじめてこころや身体の奥にある何かが動き出す。他者の影響を受けながらも、自分の主体感(Agency)は損なわれない。水平で対等な関係性のなかでダイアローグが生まれるとき、痛みは少しずつケアされ、何かが静かに変わり始めるのだと思います。
フォーラムの最後にお話ししたことを、少しだけ補足させてください。
人は、生まれたときから呼吸のようにダイアローグ(対話)をしています。まだ言葉を持たない赤ん坊は、得体の知れない不快さを感じると手足をばたつかせ、涙を流し、声をあげます。その声に、養育者たちは戸惑いながらも応えようとします。抱き上げ、揺らし、おむつを替え、ミルクを与える。ミルクを飲んだ赤ん坊は、やがて静かに眠りにつきます。赤ん坊の声に応えた養育者、そしてその応答にまた赤ん坊が応える――このやりとりこそが、ダイアローグの原点。けれど、赤ん坊と養育者だけではどうにもならないこともあります。保健師さんが訪ねてくれたり、医師がアドバイスをくれたり、本や動画から知恵をもらったり。さまざまな人の経験がシェアされ、そのなかでまた新しいダイアローグが生まれていきます。
オープンダイアローグとは、きっとそんな営みなのだと思います。
家庭や学校、職場、議会――それぞれの現場で、ダイアローグが生まれることを願っています。それは、孤立や孤独をやわらげてくれるはず。分からないことを、たくさんの人と一緒に考えていけるはずです。ぼくも、これからもオープンダイアローグの活動を続けていきます。みなさんと共に、この世界の痛みに寄り添い、未来の希望を分かち合いながら、歩んでいけたらと願っています。今日までのダイアローグを胸に刻みます。
森川すいめい
小澤いぶきさんの応答コメント
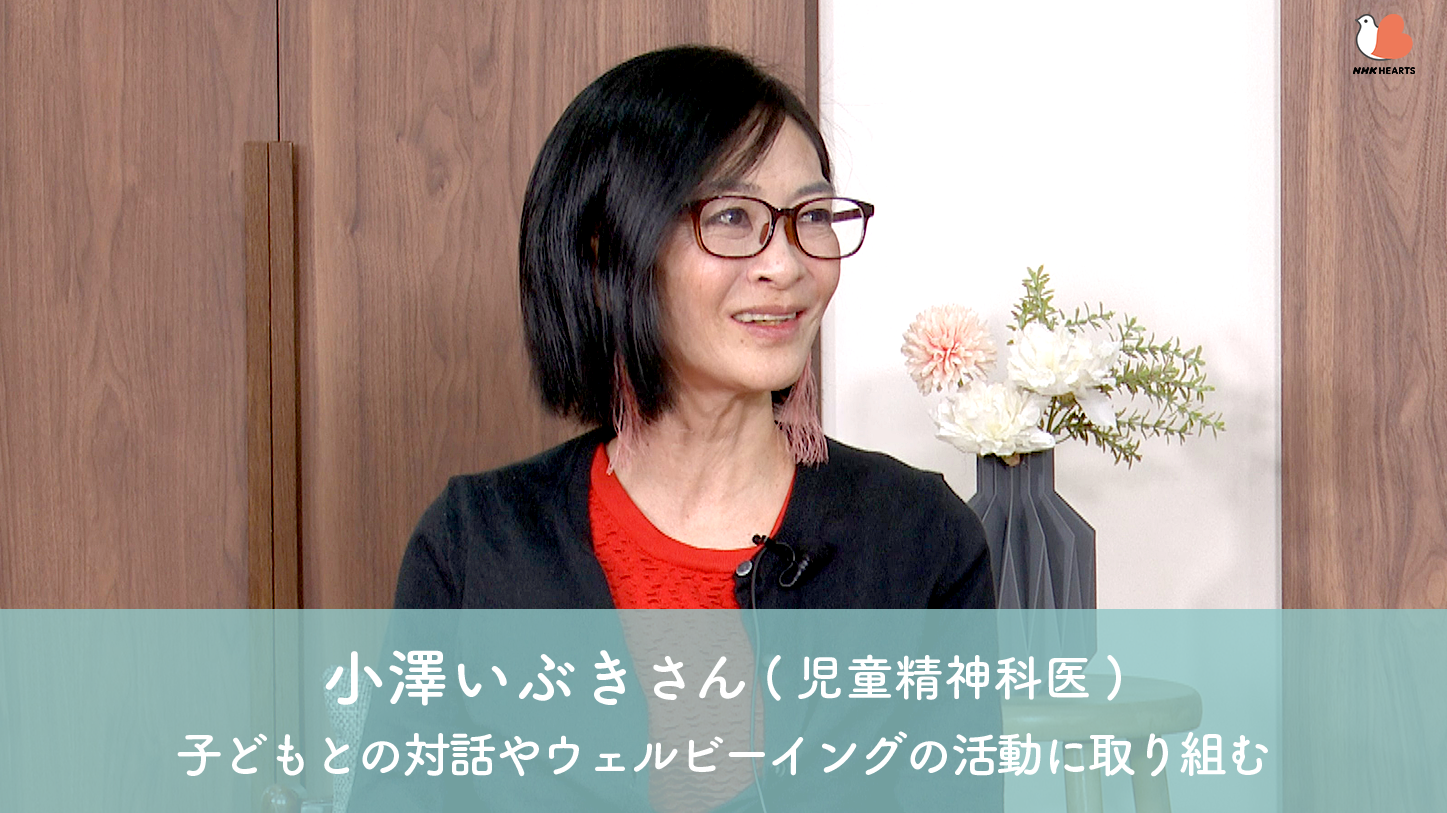
あわいのなかで
6月28日。
間(あわい)をともにしたみなさま。
ずっと対話を重ね、準備を続けてこられたみなさま。
あの日あの瞬間にあの場にいることは難しい状況にあった中で、さまざまに影響しあうみなさま。
あの場に「こえ」をおいてくださった方。
「こえ」をおかないこと・おかなくても大丈夫な余白を大切にしてくださった方。
わたしがまだまだ出会っていないたくさんの「こえ」とともにある方。
全ての方々への敬意が続く日々です。
本当にありがとうございます。
こうやって誰かに対しての敬意を「言葉にする」ことで、言葉にされない不可視化される状態があること。言葉にした途端に、混沌と揺らぐこの世界そのもの・尊厳の深淵さを漂白してしまうように感じる矛盾。言葉にされない、この世界にひびきあう尊厳そのものに大いなる敬意を感じていること。
そんなことを思いながら言葉を手繰っています。
痛み、切実さ、ままならなさ、希望、可能性、レジリエンス(しなやかさ、弾力性、回復する力)。
6月28日にいただいた「こえ」、そしてその後いただいた一人ひとりからの大切な「こえ」を感じ、何度も読み返して、さまざまな感覚を受け取りました。
受けとる中で、私の中にたちあらわれた感覚をおいてみようと思います。
本来、どのような状況・状態にあったとしても、尊厳あるAgencyのままに存在する権利を誰もが持っているということ。誰もの尊厳が存在しあい・応答しあうプロセスは、今ある「こえ」、今みえていない「こえ」、多様に存在する「こえ」とともに可能になるのかもしれないという、柔らかな兆しを感じるような感覚がたちのぼりました。
「痛み」は、それが阻まれるような何らかの権威勾配や、いびつな力の使われ方があり、尊厳に傷をつけている可能性があることのあらわれなのではないかとも思います。
そのような状況の中、一人ひとりの「こえ」が開いてきたであろう可能性、育んできたであろう社会の変化を深く感じました。
一方で、痛みを経験している時に、「自分が痛みを経験している」ということに気づくことも、気づいた時に「こえ」をおくことも、とてもエネルギーを必要とするのではないか。「誰か・どこか」だけにしわ寄せられた状況を、痛みを経験しながら伝え続けるプロセス自体にも、痛みを生み出しうる構造があるのではないか、とも感じました。
本来は、尊厳を傷つける権威勾配や力の使い方、社会のありように私も含め一人ひとりの存在がちゃんとかかわり、影響しあってきていたとしたら、痛みがひとところに閉じられるような状況がもっと少なかったのかもしれない、とも感じもしました。
一つひとつの「こえ」を感じるプロセスは、空気が柔らかく巡るように呼吸をしあい、互いの存在がひびきあい、尊厳と尊厳が相互に存在しあっていける可能性が開かれてきたことを、大切に大切に受け取るプロセスでもありました。
だからこそ、私自身も一人ひとりの存在と応答し合い、尊厳と影響し合いながら、空気が柔らかく巡り、一人ひとりが尊厳のままに呼吸をしあい、互いの存在が緩やかにひびきあうような、そんな可能性を開いていくプロセスを一緒に育んでいきたいと思います。
Sense of Being,Sense of Dignity,Sense of Agency(存在を、尊厳を、主体を感じる感覚)に耳をすませながら。
小澤いぶき
矢原隆行さんの応答コメント
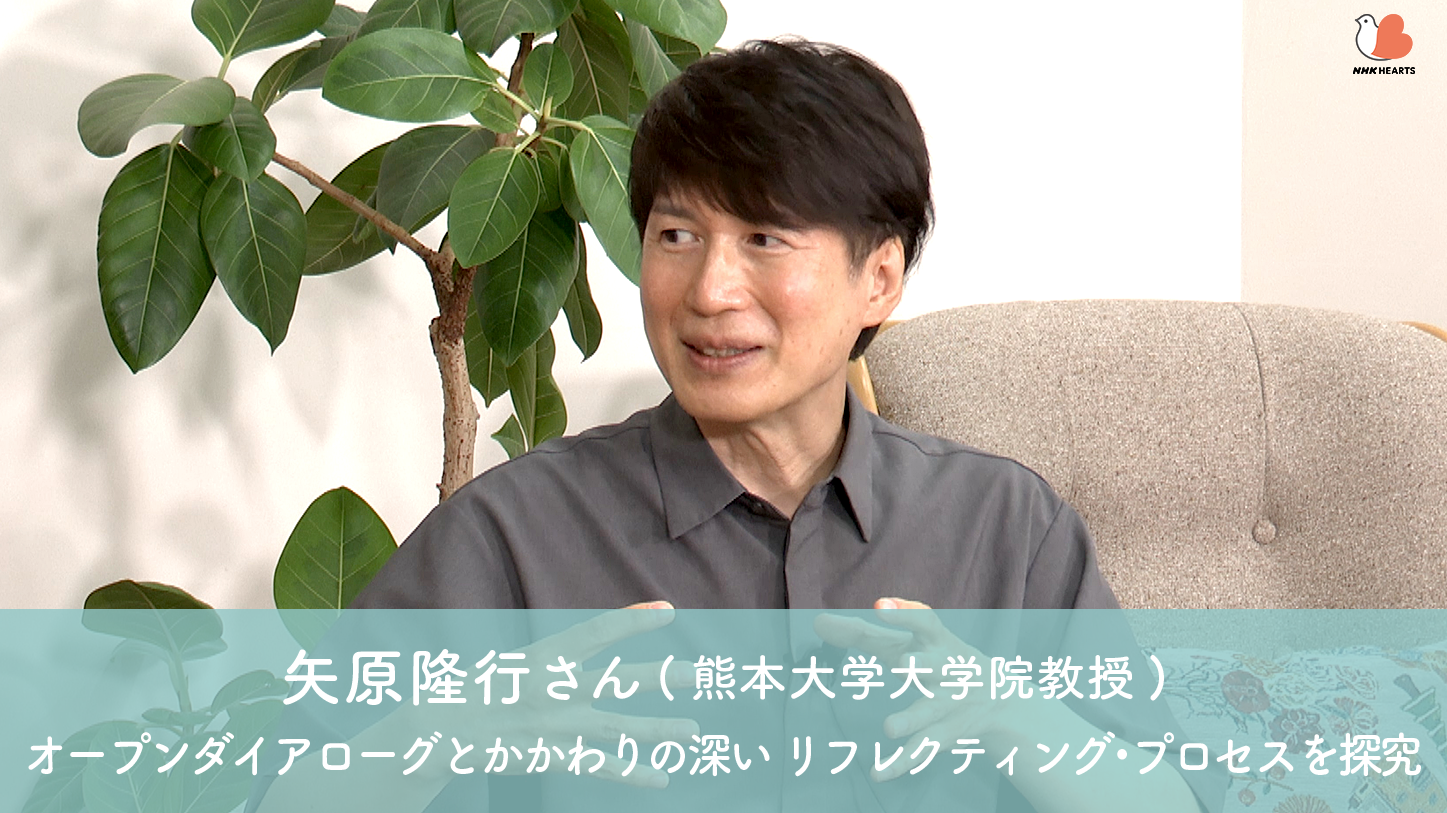
ことばは、手のようである。
6月28日のフォーラムに関わってくださったすべての皆さんに(あの日、参加することができなかった人たちにも)感謝します。
皆さんのメッセージには、当日、その場で触れたいと思い、事前に拝見することは控えていましたが、フォーラムを終えた後、すべてのメッセージと感想のアンケートを読ませていただきました。何度か読み返しながら、自分の内に溢れてきた三つの声。その会話を綴った以下の文章を、ひとまずの応答としてこの場に置かせていただきます。
C:あのとき僕たちは、どんなことばで、なにを話すことができただろう。台本や事前の打ち合わせなどいらない場であることは、皆わかっていたように思う。
苦手な照明を向けられる前から気になっていたのは、「本人・家族・支える人」と募集段階からそんな言葉で切り分けられてしまう声たちのことだ。だから、最初のターンで「ケアする/される」という枠組みを前提としない関係のあり方に触れたichifujiさんのメッセージが読み上げられたとき、そのことばに僕は背中を押してもらった気がした。
あの場では読み上げられなかった、あるいは、読み上げられるのを望まないたくさんのことばや無言の声たちも、きっと画面の向こうのあちこちに響いているのを感じながら。
P:未決定であること、ゆらぎつつ変化してゆけること。それこそがわたしたちの生きているありようです。「発達障害」「双極性障害」「統合失調症」「医師」「ソーシャルワーカー」「大学教授」「意思決定支援」「オープンダイアローグ」「対話」「水平的関係」そんな言葉で括られた瞬間、それらは凍りついてわたしたちに覆いかぶさり、あたりまえの呼吸を難しくしてしまうかもしれない。
R:けれど、診断名が今この瞬間の誰かのしんどさを支援へとつないでくれることも、肩書が制度の中で立ち回る機会を与えてくれることも、目新しい用語がなにがしか変化への期待を導いてくれることもあるはずです。流転するこの世界のなかで、言葉なしにはひとときの手がかり・足がかりを得ることも私たちにはできないのだから。
C:じゃあ僕たちは「オープンダイアローグ」の有資格者が「水平的関係」で「対話」を提供してくれるような新しい支援機関の登場を願うほかないんだろうか。もちろん、声が聞かれること、声を聞くことのできる場が守られることをたくさんの、そして、それぞれのメッセージが痛いほど訴えていたのを決して見過ごしちゃいけないとしても。
P:息を吸うように聞き、息を吐くように話すことは、わたしたちが生まれ、生きてゆくなかで、これまでも続いてきたし、これからも続いてゆくでしょう。ただ、そんなあたりまえの会話を困難にするような状況や制度が、ときに強くしがらんだ関係の中で、ときに「成果」「危機管理」「専門性」といった「正しい」言葉を盾にして、知らぬ間にわたしたちを囲い込んでしまうことがあるのもたしかです。
どうかそこに新鮮な風を通す勇気と不安がともにありますように。
R:私たちはこの社会の内に「問題」に焦点化しないあたりまえの会話を可能とするような何らかの余白をつくっていくことができるのでしょうか。そのために「オープンダイアローグ」という言葉や新たな制度を道具として使いながら。たとえば全国の刑事施設で導入され始めた「対話実践」や、いくつかの地域で始められている精神科病院への「入院者訪問支援事業」などは、はたしてそのような場になっていくのでしょうか。
C:そうした場でも、言葉や制度が凍りついてしまわないよう、僕らはもっと自由に、たんに垂直でも水平でもない、あらゆる表現としてのことばを紡いでいけるはずだ。
P:わたしたちが呼吸やことばを思い通りにコントロールしようとするのを手ばなすなら、自然な呼吸やあたりまえの会話は、いつでもいまここに溢れている。そして…
会話の続きは、きっとまたどこかで。
矢原隆行
高口恵美さんの応答コメント
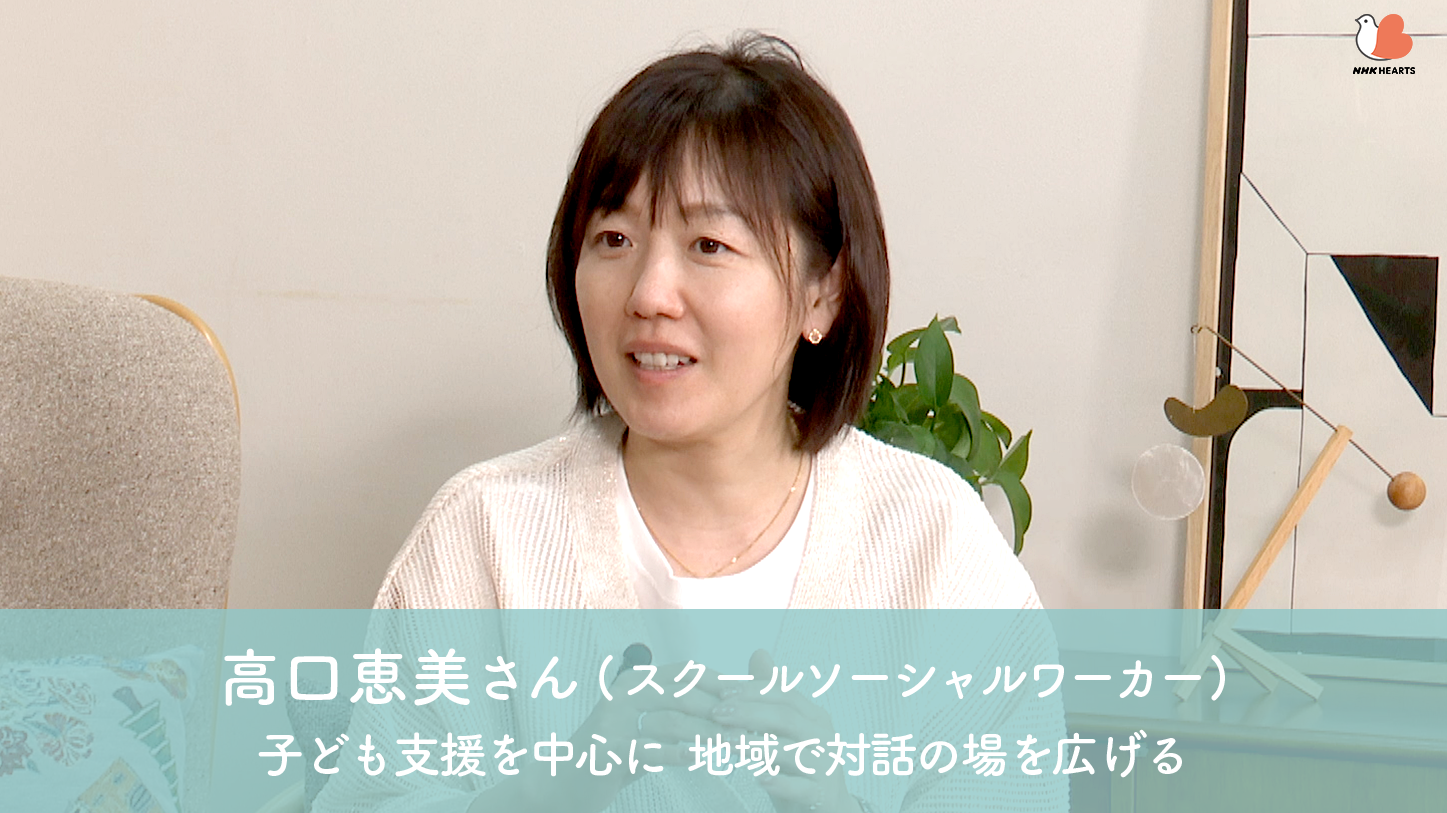
皆さま、フォーラムへのご参加と、心のこもったメッセージを本当にありがとうございました。皆さんの言葉一つひとつに触れ、今回ご参加いただいたみなさんにどのように響いたのかを感じられ、私自身深く学ばせていただいています。
「声が聴かれることの安心を実感した」という感想が多くありました。私自身あの場では、何かを解決するために発言するのではなく、「今・ここ」にある思いを丁寧に言葉にすることが尊重されていたように感じました。そうした実感をみなさんと共有できたことは、これから対話の文化を広げていくうえで大きな励みとなります。また、「一人で抱え込まなくていいことに気づいた」「専門職ではなく人としての在り方を考えた」とのコメントも印象的でした。これは、スクールソーシャルワーカーとして日々感じる「共にある」ということの力にも通ずるところがあるように感じています。日々を共にあり続けながら、支援する・されるという枠を超えて、誰もが「関わる人のひとり」として存在し、それぞれの声が響きあうような場を持つことの豊かさ、そしてその営みを通して変化していく日々。それを皆さんと分かち合えたことは、私にとっても大きな対話の贈り物でした。
一方で、「すぐに実践に移すのは難しい」という葛藤も率直に共有いただきました。その声も大切に受け止めたいと思います。わたしも目の前の社会に対して、暗黙のルールや成果、効率などの呪いの中で、これまでと違うものや不効率・不確実なものを排除する傾向も感じて「難しい」と感じることがたくさんあります。だからこそ、子どもたちや子どもたちに関わる人々(つまり全ての人)と共に、対話の時間を創造していけたらと思っています。きっと実践は「わかる」ことから始まるのではなく、「感じる」「気づく」ことから始まるのではないでしょうか。それぞれの現場や日常の中で小さなダイアローグの芽が社会に広がっていって欲しいなと願っています。
ご一緒させていただいた、全ての方に心から感謝申し上げます。
これからもみなさんと共に、揺れ動きながら、つながっていけたら幸いです。ありがとうございました。
高口恵美
お読みいただき ありがとうございました

司会の中野淳(NHK)・森川すいめいさん・小澤いぶきさん・矢原隆行さん・高口恵美さん・斎藤環さん
(制作担当者より)募集開始時から、たくさんのメッセージをお寄せいただき本当にありがとうございました。言葉で言い尽くせないほどのつらいご経験や切実な願い、日本社会や制度の課題、ご自身の実践やヒント、私どもへのご不満を含め、一つひとつのお声が「像」として目の前に立ち上がり、身につまされました。ディレクターという役割を担わせてもらっている自分が何をすべきか?「問い」をたくさんいただきました。興味をもってくださった方をはじめ、すべての方に心より御礼申し上げます。ご参加しづらかった方、音声が聞きづらかった方、アーカイブ配信をご希望されていた方、ご期待に沿えず申し訳ありませんでした。今後、品質・利便性の向上に努めてまいります。
オープンダイアローグについて詳しく知りたい方へ
森川すいめいさん監修の教材ビデオ「こころをケアする対話 オープンダイアローグ」をぜひご覧ください。無料で、いつでも・何度でも視聴できます。オンライン視聴とDVD貸し出しがあります。


